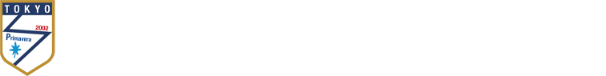column
お箸のはなし
 お箸の起源は明確ではないですが、人間が火を使うようになり、調理や食事の際に熱いものを掴むために誕生したようです。
お箸の起源は明確ではないですが、人間が火を使うようになり、調理や食事の際に熱いものを掴むために誕生したようです。日本でお箸が使われたのは、弥生時代と言われています。
箸食の文化を持つのは中国・朝鮮・台湾・韓国・ベトナム・日本などで約28%を占めます。
そのうち、箸のみを使って食事の作法が確立されているのは、日本だけです。
なぜそうなったかというと、私たちの食生活が米や魚が中心だったこともありますが、箸には、「つまむ、挟む、押さえる、救う、割く、載せる、剥がす、ほぐす、包む、切る、運ぶ、混ぜる」といった12もの機能があり、箸は指先や手の延長線で、私たちの体の一部であると言えるかもしれません。
日本人の衛生観念はもちろんですが、他人に自分の箸を使われるのを嫌がるのは、こういった日本人の箸への捉え方もありそうです。
箸のマナー違反は、知ってますか?
たくさんあるのですが、特にやって欲しくない行動は、「差し箸、ナメ箸、迷い箸、寄せ箸、噛み箸、くわえ箸、二人箸」です。
沢山あって面倒なようにも見えますが、覚えておきたい事は一つ、
「同席の方を不快にさせず、たのしく食事をとること」
これは箸に限らず、すべてのマナーに通じること。美味しいお料理も、楽しく食べてこそ、です!
料理人 齋藤清和